遺言相続
相続法(民法)の改正のポイントをまとめした!
令和元年7月1日改正
・特別寄与料
改正前は、被相続人の介護に努めた場合等の寄与分は相続人が介護を行った場合
に限られていました。しかし、公平を実現する観点から、改正後は相続人以外の者
(相続人の配偶者等)が、被相続人の介護に努めた場合でも、相続人に対して金銭
(特別寄与料)の支払を請求することが可能になりました(民法1050条)。
令和2年4月1日改正
・配偶者居住権
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合に、残された配偶者が死亡した人が
所有していた建物に、終身の間、無償で居住することができる権利です。
→配偶者居住権は、建物を所有するのではなく、単に居住するだけの権利です。
したがって、配偶者居住権は所有権よりも低額な権利です。そのために遺産分割に
おいて、残された配偶者が配偶者居住権及び預貯金の両方を取得したりすることが
可能になります。
改正前は、所有権しか存在しなかったために、配偶者が建物の所有権を取得して
しまうと、相続人間の公平を図るために、他の相続人に代償金を支払わされたり、
預貯金の取り分が少なくなったりして、配偶者の生活が困難になるケースが多数
ありました。
遺言書を法務局が保管する制度が始まりました!
令和2年7月10日施行 遺言書保管法
・自筆証書遺言の保管制度
法務局にて、自筆で作成した遺言を保管する制度が
新たに創設されました。法務局で保管する事により
遺言書紛失の恐れがなくなり相続人等の利害関係者
による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐ事ができ
ます。
遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書
遺言の形式に適合しているかについて、外形的な
チェックを行うので、相続開始後に家庭裁判所における
検認が不要となります。
生前→遺言 死後→相続
遺言
遺言書を作成する最大の目的は、相続人間のトラブル防止です。
自筆証書遺言作成フルサポート
自筆証書遺言は、文面のすべてを本人が自筆しなければなりません。
当事務所では、お客様(遺言者)の遺志・要望をお伺いした上で、文面のすべてを
作成します。その後にお客様(遺言者)に自筆して頂きます。
紙(良質紙)・封筒・筆記用具は当事務所がすべて負担します。
山川行政書士事務所では、様々な要望に応じて豊富な文例を準備しています。
自筆証書遺言の要件
全文・日付・氏名を自書して押印することが必要です。
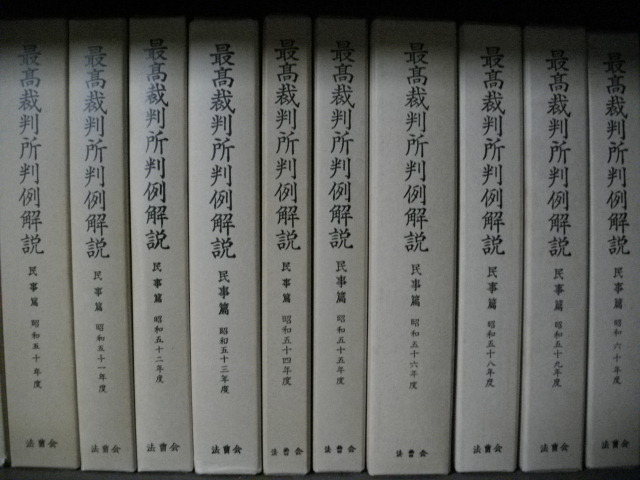 全文: 全文:
録音・録画→無効
ワープロ→無効(東京高昭59.3.22)
代筆→無効
添い手→無効(最判昭62.10.8)
カーボン複写→有効(最判平5.10.19)
日付:
吉日→無効(最判昭54.5.31)
誕生日→有効
氏名:
氏名の一方のみ(本人を特定できる)
→有効(大判大4.7.3)
通称・ペンネーム(本人を特定できる)→有効
押印:
認印→有効
拇印・指印→有効(最判平1.2.16)
公正証書遺言作成フルサポート
当事務所では、お客様(遺言者)の遺志・要望をお伺いしたうえで、公正証書原案を
作成して、公証役場にて公正証書遺言を作成します。
公証役場の手配・証人の準備などはすべて当事務所が行います。
遺言執行手続き
遺言で遺言執行者を指定しておくことにより遺言の内容をスムーズに実現する事が
可能となります。相続人間のトラブルを防止する事ができます。
遺言執行者は法律の専門家を指定する場合がほとんどです。
遺言執行者に行政書士山川哲生を指定した場合、相続開始後(遺言者の死亡後)
すみやかに行政書士山川哲生が遺言執行手続き(相続財産目録の作成及び交付、
不動産・預貯金・有価証券などの名義書換など)を行います。
相続
被相続人が死亡した時点で相続開始となり、相続手続きが必要となります。
相続手続きスケジュール
死亡日(相続開始日)
↓
7日以内:死亡届を市区町村役場に提出(死亡診断書または死体検案書添付)
↓
遅滞なく:遺言書がある場合は遺言書の検認を家庭裁判所に請求
↓
↓ ・相続人調査、相続財産調査
↓ ・特別代理人の選任申立て
↓ ・遺産分割協議書の作成
↓ ・遺言執行
↓ ・不動産、預貯金、株式等の名義変更 など
↓
3ヶ月以内:相続放棄又は限定承認(家庭裁判所に申述)
↓
4ヶ月以内:被相続人の所得税の準確定申告・納付
↓ (1月1日から死亡日までの所得)
↓ (サラリーマンは会社で行ってもらえます。)
↓
10ヶ月以内:相続税の申告・納付
↓
1年以内 :遺留分減殺請求の消滅時効
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは相続開始後(被相続人の死亡後)に作成するものであって、
相続人間における遺産分割の協議(話し合い)の内容をまとめたものです。
相続人全員の協議がまとまった場合、当事務所が相続人間の協議の内容をお伺い
した上で、遺産分割協議書を作成します。
相続人の調査・確定
法定相続人を正確に調査して確定しておかないと、もし、法定相続人に間違いが
あった場合、相続手続きを初めからやり直さなければならなくなる事があります。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍謄本)
を調べなければなりません。前婚歴・前婚の子・認知した子などがいないかを調べ
なければなりません。
当事務所では、被相続人・相続人の戸籍謄本等を代理取得し、相続権を有する法定相
続人を調査・確定します。その後に法定相続人を表す相続関係説明図を作成します。
相続財産の調査・確定
相続財産を全て洗い出して調査・確定しておかないと、もし、相続財産に間違いが
あった場合、相続手続きを初めからやり直さなければならなくなる事があります。
当事務所では、被相続人の相続財産を調査・確定して相続財産目録を作成します。
|

メール相談は完全無料
お気軽にご相談下さい。
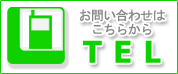
電話相談は完全無料
お気軽にご相談下さい。
0568-91-3548 |